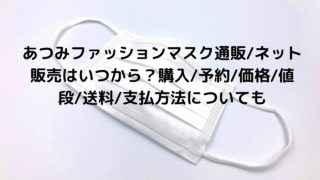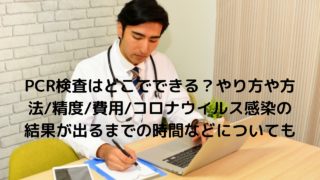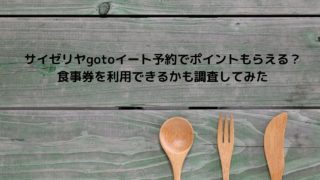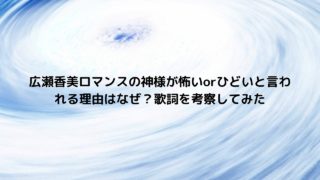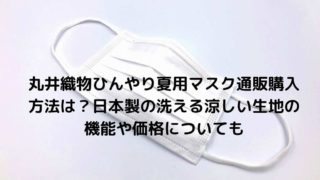新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、影響を受けて会社法人や個人事業主、一般の国民に向けて政府や自治体は、多くの助成金、給付金、協力金などが支給されています。
この記事については、申請や金額面ではなくもらった後の、確定申告について考えていきたいと思います。
何かというと毎年、収入に対して確定申告を行うことになりますが、この受け取った金額を収入として考えるなら所得が増えるので、税金をおさめることになります。
どれが課税、どれが非課税か調べていきます。
ギリギリに悩むより、今のうちに考えておくと焦らずに済みますよね。
目次
コロナ助成金/給付金で税金のかかるものは(課税)
収入となるものについてご説明していきますね。
見ていくと分かるのですが、税金がかかってくる助成金や給付金などは、商売をしている商工業者に関連するものが当てはまってくるようですね。
持続化給付金
持続化給付金は、一番話題になっている給付金ですね。
国が支給する給付金で、5月1日から申請がはじまって殺到していますが、何かというと今年に入って、1ヶ月どこかの売上が、昨年の同月と比較して50%以上減少している場合に対象となります。
金額は法人事業者で最高200万円。
個人事業者で最高100万円です。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
感染拡大防止協力金
感染拡大防止協力金は、東京都が休業要請をして応じた事業者に支給される協力金で、各自治体によって金額や名前も違ってきます。
10万円ぐらいから50万ぐらいの金額が支給されています。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、新型コロナウイルスの影響で仕事などがなくなり、会社の支持で従業員を休業させた場合に、休業補償を支払う必要があるのですが、その一部が助成される制度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
小学校休業等対応助成金
小学校休業等対応助成金は、新型コロナウイルスの影響で、小学校などが休校し子供を世話をするために休む必要があったときに、会社が有給休暇を別であたえて休ませた事業者に対して助成される制度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
小学校休業等対応支援金
小学校休業等対応助成金は、新型コロナウイルスの影響で、小学校などが休校し子供を世話をするために契約した仕事ができなくなった保護者を支援するため、助成される制度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
上記の助成金/給付金は課税対象で税金がかかってきます。
もともと、事業者の売上が減少したことに対する補填や給与賃金など必要経費に参入するべき経費の補填なので、税金としては事業所得になります。
雑収入に計上する形になるかと思います。
課税される根拠は国税庁より取り扱いの文書が出ています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
コロナ助成金/給付金で税金のかからないもの(非課税)
コロナ助成金/給付金の中でも税金のかからないものもあります。
上記は、事業者向けのものでしたが、こちらは一般家庭向けの制度で税金のかからない収入になります。
特別定額給付金
特別定額給付金は、一番気になってた1人あたり10万円支給されえるといわれていた給付金ですね。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯への臨時給付金は、中学校以下の子供1人につき10,000円支給されますね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/rinjitokurei/index.html
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/sitter_atsukai.html
ベビーシッター利用支援事業における助成
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kodomo/hoiku/bs/bs2nendo.html
まとめ
現状は上記のような給付金/助成金があり、制度によっても課税か非課税か違ってきます。
ただ、このような状況下であり、売上の補填的な役割があるので、黒字になることは少ないけど、計算方法自体で全部ではないかと考えられる。
非課税枠を拡大してはどうかとの意見も出ているそうですが、今のところはこのような感じです。
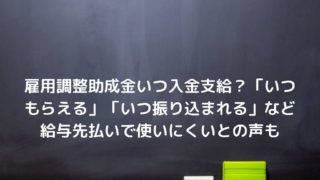


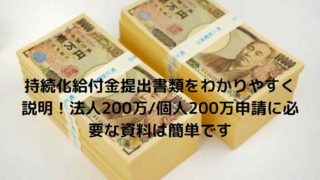



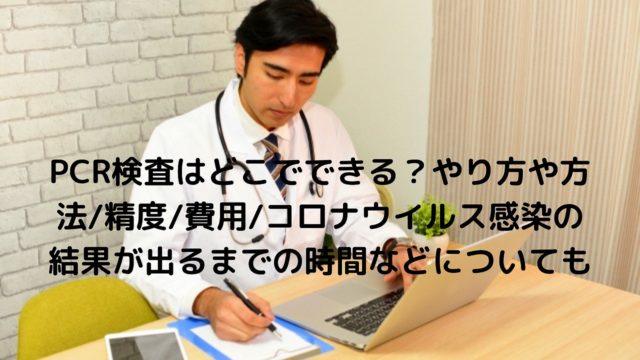

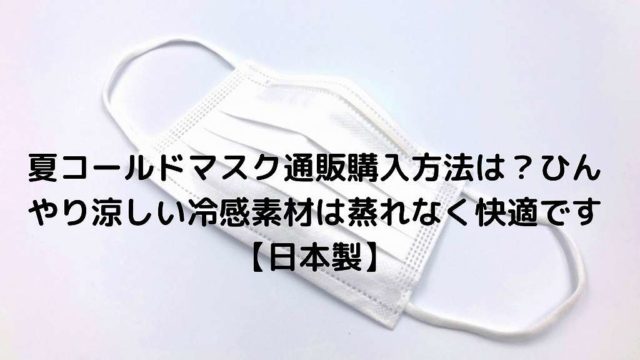
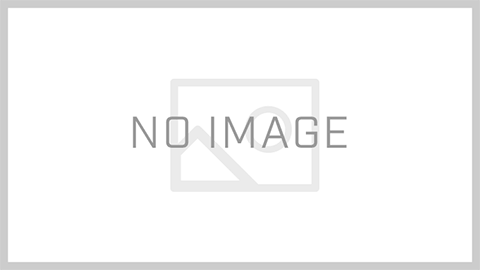
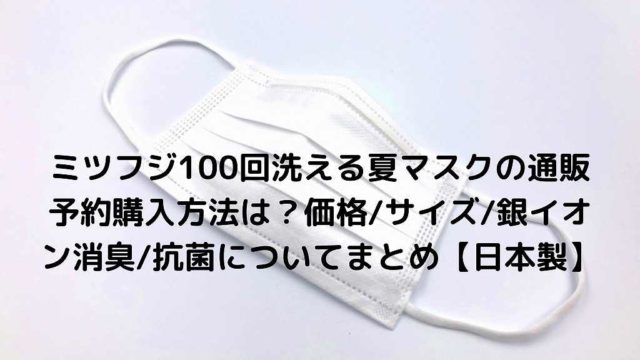
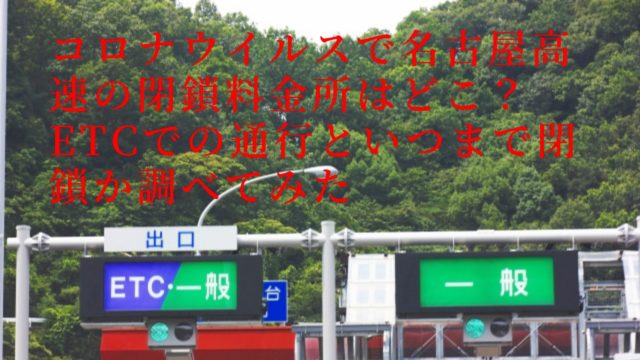
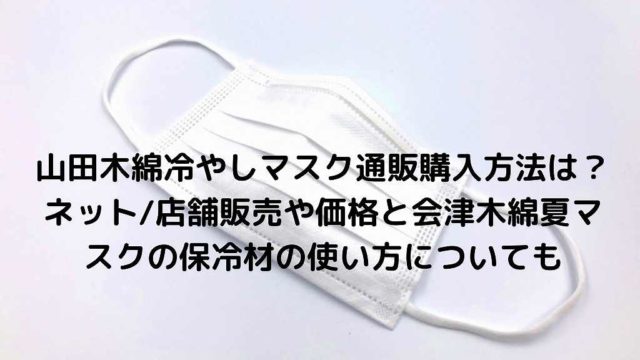
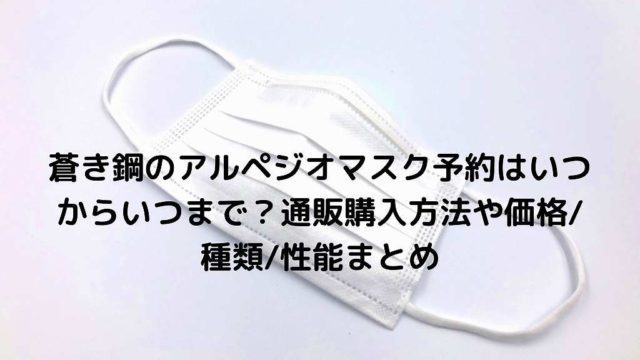
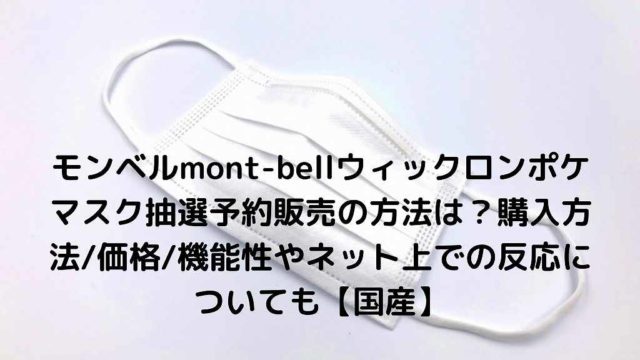
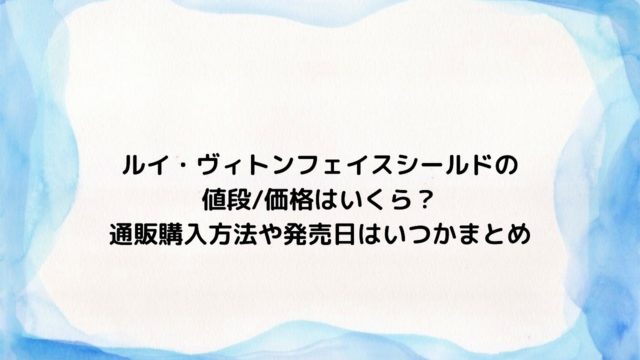
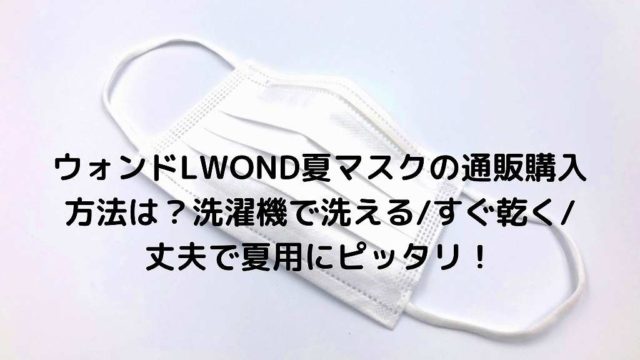
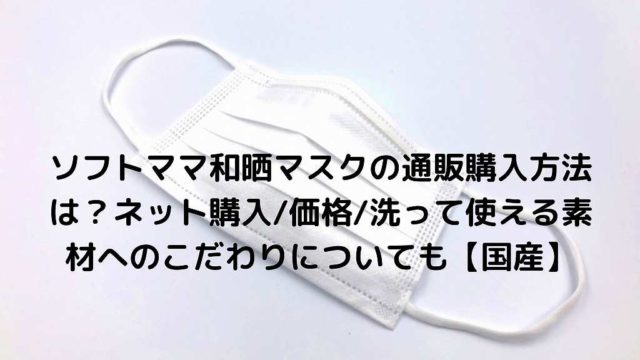
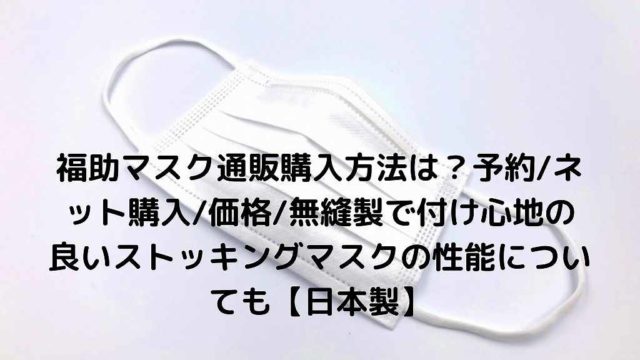
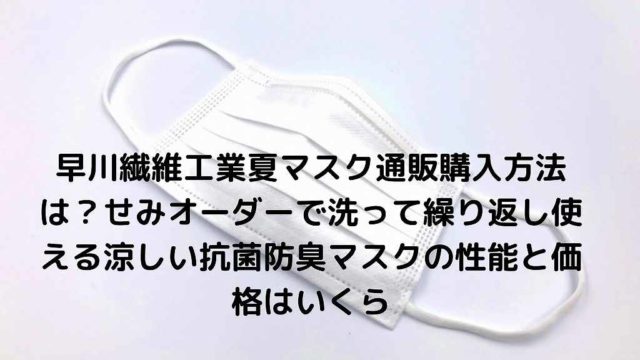
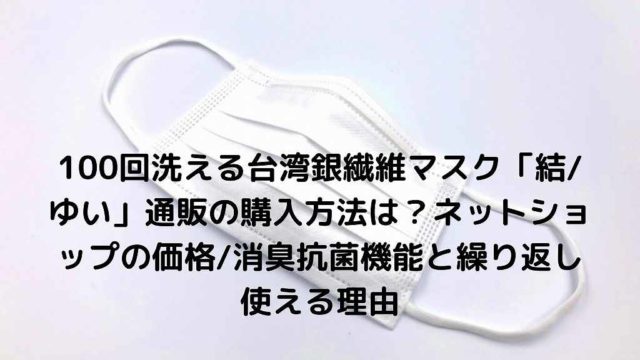
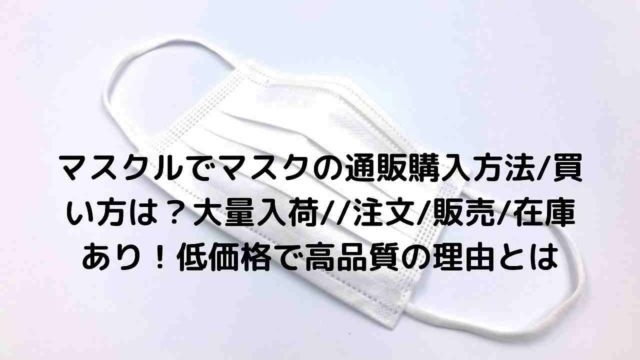
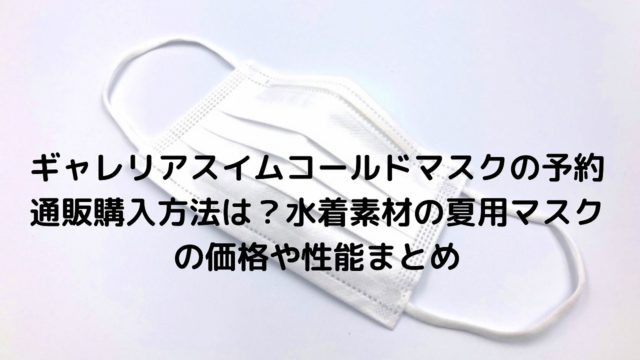
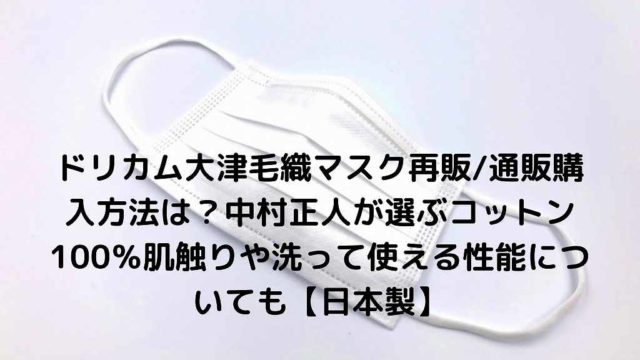
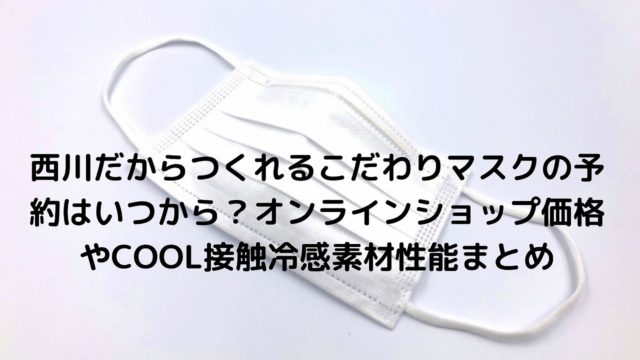
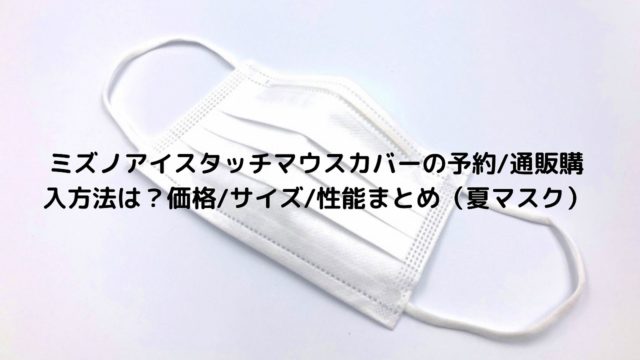

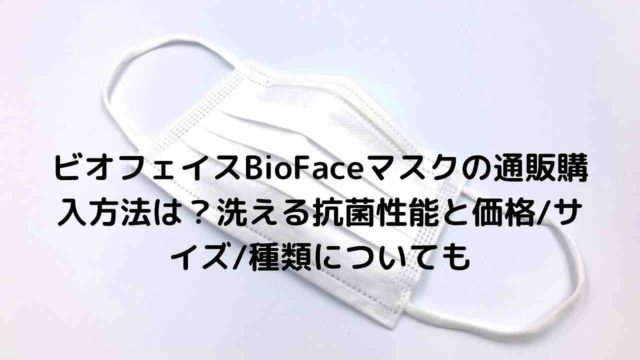
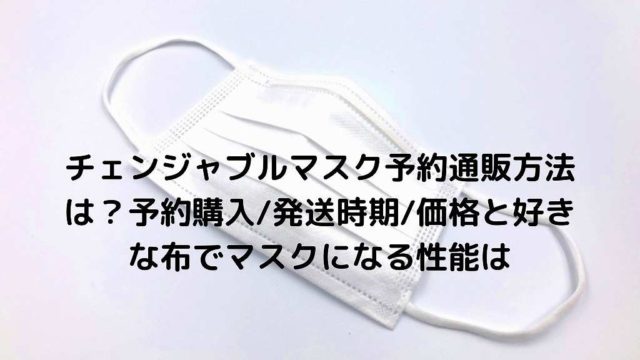
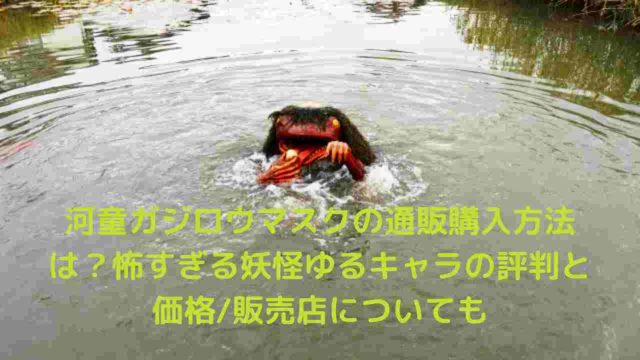
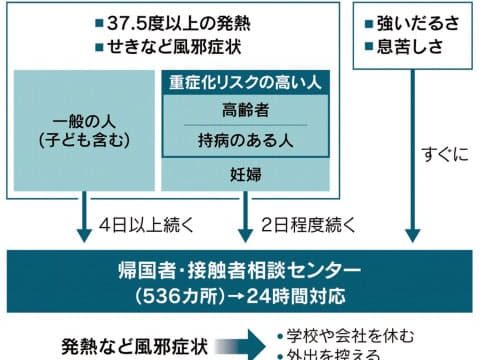
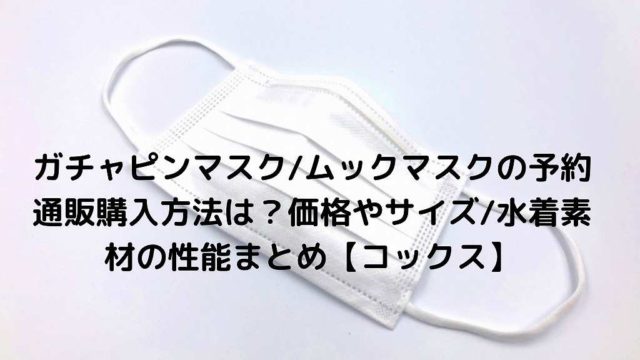
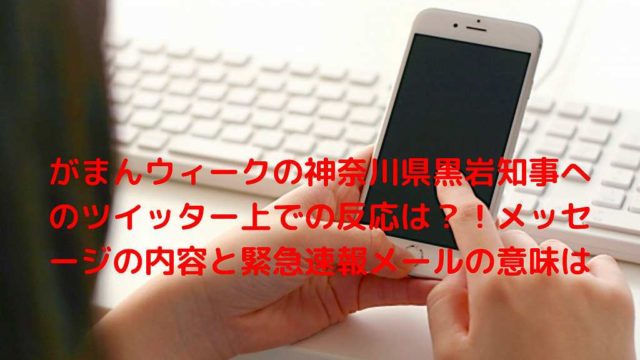
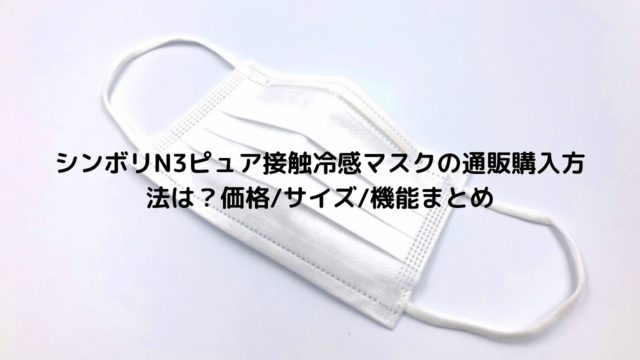
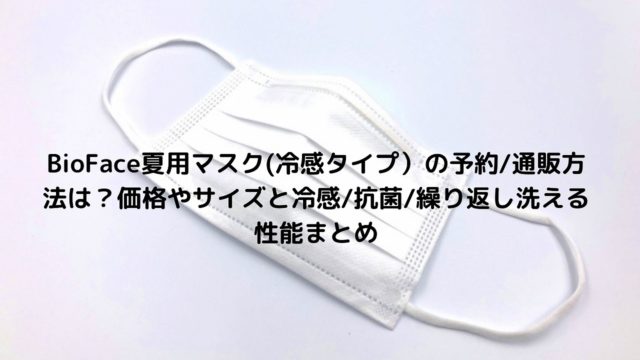
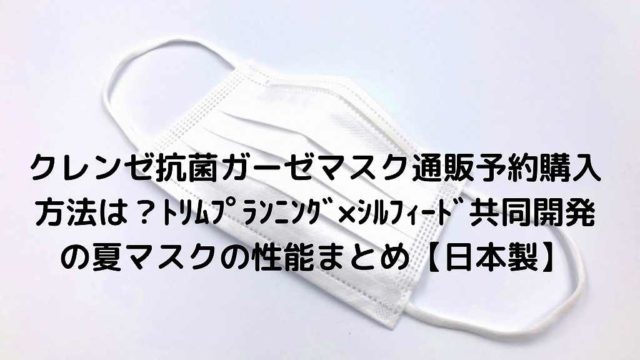
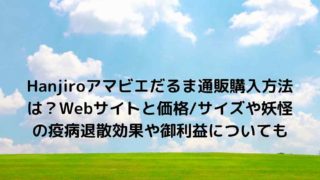
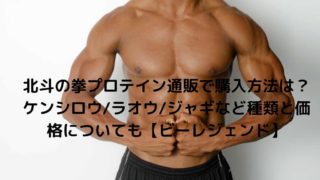

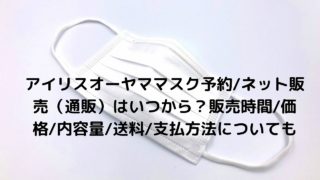
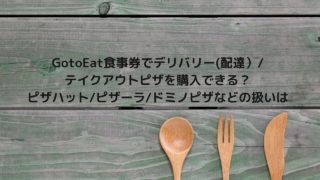
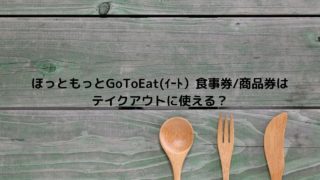
はいつから?価格_内容量_送料_支払方法についても-320x180.jpg)